トップへ 本棚へ
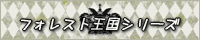
暗闇の淵 ドクドクと流れていく命のかけら。燃えるような熱い傷口に比べて、段々と冷えていく指先。少しずつ感覚がなくなっていく。 …………ああ、あと、どれだけの血を流したら死ぬのだろう? 漠然とした思考が朦朧とした意識を過ぎる。 不思議と、死ぬことについて恐怖はなかった。今まで、自分はどれだけの苦痛に耐えてきたのか、それを考えるとちょっとだけ馬鹿らしくなった。生きるということにしがみついていた自分が悲しい。 死ねば、もう全てが終わる。この果てない悪夢のような日々からも。 それでいい。もう、何も望まないから……。 終わらせてくれ……。 ……終わらせて……。 …………終わるのだ……。 ……もう、全て………。 バンバンと何かを叩く音がして、俺の意識は急速に現実に引き戻された。 一瞬、自分のいる場所がわからなかった。ふかふかの寝台に沈んだ身体。柔らかなシーツが優しく包み込んでいる。 感覚がなくなっていた指先に痺れを感じて、俺は上半身を起こした。 整然と整えられた部屋。一見して高価とわかる家具がうるさくない程度に並んでいる。何だか、高級宿の一室のよう。 ……ここは? 思考がついていかない。どうして、こんなところに俺はいるのだろう? あの日、自分は死んだのではなかったか? じゃあ、ここは死んだ魂が生きつくという天界か? 神々が住まうという……。 神々だって? ……いつから自分は神を信じるようになったというのか? 神々といっても、この国の信仰では神は人を救ってくれる有り難い存在じゃない。他の国では神をあがめ祭ることで救いがあると信じているようだけれど、フォレスト王国では神は世界を創り、世界を支え、世界を動かす存在で、それは足元に土があって、空には雲が流れるといったような自然と同化しているもので、人々の救済なんてしてくれない。 ただ一つ、神がしてくれることは死んだ者の魂を導き新たに転生させるという。生きている人間を救うことなんてしない。 だから、神なんて存在を初めから認めていなかったはずだ、自分は。 ……どこかですがっていたのか、俺は。 バンバンとまだ音がしている。どこからだろう? 顔を上げて、音に耳を澄ます。外からだ。裸足のままで、寝台を降りた。床に敷かれた絨毯が心地よい。 靴は? 服は? ぼんやりと身支度をしなければ、と思う。でも、音が自分を呼んでいるような気がして、シーツを上半身にまとって、それを引きずりながら寝室らしき部屋を出た。ドアをあけるとそこは居間らしい。音は居間のドアの外から。 バンバンバン、と叩かれる音に考えるのをやめて俺はドアを開けた。 ドアを叩くために振りかぶったらしい拳が空振りして、俺の前に前のめってきたのは金髪の少年。……誰? 「お前は寝起きが悪いほうか?」 少年は前かがみの姿勢から背筋を伸ばして、俺を睨み上げてきた。大きなエメラルドグリーンの瞳とキリッとした眉が印象的な面立ち。その存在の内側からこちらを圧倒してくる眩い光のような感じはこの少年が持つ魔力のせいか。こんな桁外れの魔力は……。年のころは十代前半……十三か、四といったところだろう。少年の横ではこれまた茶色の髪に茶色の大きな瞳が眠たげに目じりがたれさがった少年がいる。どこかで見知ったような……。 「……カイ?」 たれ目の少年に呼びかける。少年は「おはようございます、ロベルトさん」と挨拶してきた。 「……おはよう」 そっと返したところで、カイと俺との間に金髪少年が割り込んできた。不機嫌そうな顔で俺を睨む。 「俺を無視してんじゃない」 「……っ」 喉まで名前が出掛かったけれど、声が出なかった。頭が回りきれてない。 俺は生きていて……いるらしい。 ……ああ、そうだった。あの日、死ぬのだと思ったけれど、生きながらえて……。 そして、俺は……。 「お前、寝ぼけてるだろう」 ……そうかもしれない。悪夢はまだ続いていて、いまだに俺をあの日に引き戻すから……。現実に立ち戻るのにひどく時間がかかってしまう。 「俺のこと、覚えてるか? 昨日、一応、顔合わせしたときに名乗ったと思うが」 少年は片手を腰に当てて、胸を張っては俺を見上げてきた。年上の俺を前にしても物怖じしない態度。豪胆な。まあ、彼の魔力を思えば俺と少年の力関係は少年のほうが上だろう。俺たち魔法使いは年齢に関係なく、魔力が強い者が上に立つ、実力主義だ。 隣のカイが俺と少年を交互に見やり、何やらビクついている。少年の剣呑な態度に喧嘩になるのではないかと心配しているのかもしれない。 喧嘩なんて……。 「……クエンツ様」 俺はそこでようやく、金髪少年の名前を口にした。それをきっかけに怒涛のように押し寄せるあの日から昨日までの記憶。 そうだ、俺は……。 昨日、フォレスト王国宮廷魔法師団の一員として王宮に迎えられた。ここは王城の敷地内にある魔法師団の寮の俺のために用意された部屋だ。 そして、目の前にいるのが魔法師団で一番の実力者ディード・クエンツ。 現国王の甥っ子である彼は、六年前、父親が犯した謀反事件の咎を受けて王族から排斥された。本当は処刑されそうになったらしいが、国王ゼノビア陛下の温情から処刑を免れ王妃の実家であった七家の一家クイーン家に預けられた。そして、昨年十六歳のときに宮廷魔法師として再び王宮に召還された人物だ。 十代前半に見える外見だが、……十七だった。そして、カイは魔法学校の同期生で俺と同じく昨日、宮廷魔法師になった。彼も十八歳だ。二人とも童顔だ。 「ディードでいい。俺もお前のことはロベルトと呼ぶからさ」 「……はい」 頷いた俺の胸元をディードは押してきた。不意をつかれた俺はよろよろとよろけてしりもちをついた。 「わっ、デ、ディード様、何されるんですか? だ、大丈夫ですか、ロベルトさん」 カイがディードの脇をすり抜けて俺に寄ってきた。そこで、大きな目をギョッと見開いた。……何だ? その表情の変化に訝しげていると、俺の前に立ったディードが指をこちらに突き刺してきた。片手には俺から剥ぎ取ったシーツが握られている。 「お前、何だ、それは」 怒ったような声で問いかけてくる。ノロノロとディードの指先を辿って、俺は寝巻きがわりのシャツの、はだけた自分の胸元を見た。血色の悪い肌にまだらに染み付いた痣の数々。 ああ、カイが驚いたのはこれか、と納得する。痣だらけの男の裸なんて見ていて気持ちのいいものではない。 俺はそっとシャツの前をかき合わせた。 「見苦しいものをお見せしました」 平坦な声で言って、頭を下げた。 「俺が聞いたことは無視か、お前」 低く怒りを押し殺したような声を吐くディードを見上げると、彼は指先をパチンと鳴らした。途端、バケツをひっくり返したような水が俺の頭に振ってきた。 「…………」 「ディード様?」 巻き添えを食らって半濡れになったカイが仰天してディードを振り返る。室内で水を降らせるなんて、宮廷魔法師の俺たちには何てことないことだが、いきなり、人に水をぶちまけるという行動の理由がわからない。 「これで、目が覚めたか? 五分、時間をやるから着替えて来い。その間に、俺の質問に対する答えをまとめて来な」 「……質問…とは……」 「その痣が何なのか、誰に付けられた? どういう理由で? その三つに最低限答えろ。でなければ、お前の宮廷魔法師としての採用はなかったことにする」 一瞬、頭が真っ白になった。採用の取り消し? 別に宮廷魔法師になりたくてなったわけではないのだが……この場を追い出されたら、俺はどこに行けばいい? 振り仰いだディードはもう俺ではなくカイを見ていた。少しばつが悪そうな顔をしてカイに謝罪する。 「悪かったな、カイも着替えて来いよ。でも、早く戻って来いよ」 さっきまでの怒りは微塵もなく、さっぱりとした笑顔で優しい声音。カイは「はい」と飛び上がるように部屋を出て行った。俺はその一連の動きを相変わらずしりもちをついた姿勢で見ていた。 と、ディードの腕が俺に伸びてきた。俺は殴られるのではないかと反射的に顔を庇うように腕を上げた。その腕を掴んで、ディードはグイッと俺を引っ張り起こす。 「お前もさっさと着替えろよ。風邪をひかれると俺としても後味が悪い」 苦虫を噛み潰したような顔で俺を睨み上げる。 俺はそっと頷いた。寝室に舞い戻る。居間へと続くドアとの反対側にバス室がある。 「濡れた服は脱衣所のかごに入れておけ。後で洗濯係が洗ってくれる。部屋の掃除も係の女官がしてくれる。だけど、部屋に入られたくなかったら、前もって言って鍵をかけとけ。洗濯物は地下の洗濯室に直接持っていけばいい」 ディードが俺の背中に説明してきた。振り返った俺にディードは怒るでも笑うでもない幼い少年顔でこちらを見ていた。俺は頷いて、寝室のドアを閉じた。 …………あの少年が、ディード・クエンツ。想像と違った。 謀反人の息子というだけで、処刑されかかった過去を持つにしては悲壮感などない。 俺はもっと自分に近い人間かと想像していたけれど。 ……あの、眩い光のような魔力といい、物怖じしない態度といい、喜怒哀楽のハッキリした感情表現といい……。 全然、俺とは違う。 クローゼットから宮廷魔法師の制服を取り出す。黒の詰襟の上着に同色のズボン。シンプルなデザインだが、生地の素材は手触りから言って高級そのもの。それを片手にバス室に向かう。洗面所と別に区切られたバス室にはバスタブにシャワー。これが各個人の部屋に備え付けられていて、湯は常時、出るというから凄い。 脱衣所でぬれた服を脱いで、壁に添えられた鏡に醜い裸体を晒した。痣がまだらに白い肌に浮いている。自分の身体でも、気持ちが悪いと思う。 だが、皮膚に沈着してしまった痣はもう二年近く経過するというのに、消える気配がない。怨念がこもっているのだろう。 母親譲りの中性的な顔立ちは、特出するものがあるわけではないが、男である俺の存在感をあいまいにした。 母と同じ薄茶色の髪も薄い緑色の瞳も、愛人の存在を見せ付けるためにあるような俺を正妻がすんなりと受け入れられたはずはなく、夫に対する恨みは全て暴力となって愛人の子であった俺に向かってきた。それが痣の理由。 ディードの質問に答えるにはそれだけで十分だろう。 鏡の自分から視線を逸らして、俺は制服に着替える。 父親が家のためだけに娶った正妻にあてつけで、俺の母親と関係を持ったことも。その母親が死んで、跡取りがいないという理由で父親が俺を引き取って、そして、正妻の俺に対する虐待行為を知っていて黙認していたことは……ディードが知る必要のないことだ。 誰も知らなくていい。生きるに値しない俺なんかのことなど。 死ぬことすらできなかった俺なんかのことを。 誰も知る必要はない。 この深い闇を誰も覗くことはない。 ここには絶望しかないのだから……。 「暗闇の淵 完」 |