トップへ 本棚へ
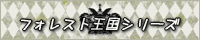
暗闇の記憶 暗闇の中で、ジッと息をひそめていた。 見つかれば、また、あの人は俺を叩くだろう。 幼い頃の俺は、自分に向けられる暴力の意味がわからなかった。ただ、その痛みから逃れることだけを考えて、あがいた。 あの人に見つからなければ……。 そう思って、頭からシーツを被り、クローゼットの奥に身を縮めた。握った拳の指の先から段々と、震えが身体中に広がる。ガチガチと鳴る歯の音が暗闇の中でやけに響く。 ありえないことだが、そのときの俺は、そんな些細な音もあの人の耳に届くのではないかと、恐れた。 音を殺すように、唇を噛む。 そうして、力を入れすぎたのか、柔肌を歯が突き刺し、口の中に血の味が広がった。 唇を切った痛みは、あまりなかった。 常日頃から繰り返される暴力の方が、まだ痛く、辛い。 口の中に溢れる血を、静かに嚥下した。 ドクドクと身体の中心で脈打つ鼓動が、昔、母親に連れて行ってもらった祭りで聞いたドラムの音のように身体の奥から、揺さぶっては響く。 まるで、内側から身体を突き破るように大きく激しく早く――。 もう、そのまま、心臓だけ飛び出すのではないかと、思った。 そんな俺を包み込んだ闇は、だけど長くは続かない。 外から聞こえる足音がやがてこちらに近づくと、クローゼットは開かれた。 隙間から差し込んでくる光に、希望なんて何もない。その先にあるのは生まれてきたことを呪う絶望だけ。 引きずり出された身体は、冷たい床に叩きつけられる。冷たいと、感じるより先に、飛んできた靴先が腹をえぐって、俺は胃液を吐いた。 頭上に聞こえるのは、錯乱染みた奇声。それは俺を罵倒し、蔑む。 幼かった俺には、その言葉の意味を完全に理解することは、できなかったけれど。そこにある憎悪はわかった。 自分を嫌っていると、ハッキリとわかるほどに、あからさまな雰囲気に、俺は何故この人にここまで嫌われなければならないのか、不思議だった。 母親が死んで、身寄りがなくなった俺をこの家に連れてきた男は、この人が新しい母親になるのだと言った。 なのに――。 母親とは優しく暖かなものだと、俺の短い人生で築き上げられた定義はあっけなく壊されるのに数日とかからなかった。 嫌われているのなら、好かれようとその後の俺は努力をした。 笑いかけてみれば、頬を打たれた。 痛みを訴えると、また逆の頬を打たれた。 泣いたら、突き飛ばされた。 悲鳴を上げれば、身体を叩かれた。 声を押し殺しても、暴力は止まない。 終わりを俺は知らなかった。 意識を失って、目覚めれば暴力は終わっていた。けれど、また次の暴力が始まるのに、それを終わりと言って良かったのか。 いつしか、物心がつくころには何をしても無駄なのだと悟った。 抗うことすら無意味なのだと、心を殺した。 何も感じなければ、痛みすらどうでも良くなる。 終わりも始まりも、何もかもがどうでも良くなって、自分すら放棄した。 もう笑うことなんてないと思っていた。 ずっと、暗闇の中で生きるのだと思っていた。 彼に会うまでは……。 「失礼します、団長。お呼びだそうで」 ドアをノックし、応答がある前にドアを開けた。答えを待たなくても、室内に彼がいることは同じ魔力を持っている者ならわかる。内側から圧倒する黄金色の光。眩しい太陽のような強烈な力。 でも、室内にはもう一人いる。冷ややかな、身も凍るような魔力の主は……。 「シリウスさんも呼び出されたんですか?」 執務机の前に立っているのは、銀髪の麗人シリウス・ダリア。すらりと背筋を伸して立つその姿勢の良さに、目も眩むような美貌。切れ長の目元は涼やかではあるが、青灰色の瞳は俺を横目に見ると、 「ロベルトか。いや」 俺の名前を確認するように口にして、シリウスは冷ややかに、否定した。 「シリウスは任務の報告だ」 執務机の向こうからそう言うのは、この部屋の主で、新国王即位に対しての人事編成により新たに宮廷魔法師団<<十七柱>>の団長に任命されたディード・クエンツ、その人である。 俺より三つ年下のはずで今年十九歳になるはずなのに、外見は十代前半にしか見えない童顔。その幼い顔立ちを不機嫌そうに歪めて、ディードはエメラルドグリーンの瞳で俺を斜めに見ると、言った。 「お前とは違う」 「……俺、何で呼び出されたんですか?」 小首を傾げて問いかけた俺に、ディードは片手をこちらに突き出した。 「少し待て」 顔を顰めたまま、ディードは手にしていた書類に目を落とす。 団長に任命される際、「絶対に嫌だ」と駄々をこねた彼だったが、生来の生真面目な性格からか、仕事は真面目にやっている様子だ。 もっとも、この生真面目な性格ゆえに、新国王であるジルビア陛下とはそりが合わず、顔を付き合わせては喧嘩ばかりしている。喧嘩と言っても、ディードが陛下を嫌っているだけで、陛下にすればディードは実に良い反応をしてくれるオモチャであるのだろう。 彼ほどに感情に直情的な人間は、建前を必要とする上流社会ではあまりいない。 それが俺には驚きだった。彼の出自は元王族。先代国王ゼノビア陛下の甥で、現国王ジルビア陛下の従弟であったが、彼の父親が起こした謀反事件により、十一歳のときに謀反人の息子という汚名を与えられた。それだけならまだしも、遺恨を嫌った王宮の官僚たちにより処刑されそうになったという――波乱万丈の人生を送っていた。 彼に出会うまで、愛人の息子であったがために、正妻に虐待され、殺されそうになった俺とディードの立場は似ているような気がしていた。 立場は似ているかもしれない。だが、人間としては全く、別物だった。 心を殺し、感情を捨てた俺に対して、ディードは再び王宮に召還され、今度は王族に仕える宮廷魔法師という立場に身を置きながら、決して腐ることなく心を自由にしていた。 どうして、そんなに自由にいられるのだ? 俺は彼を前にしていると、自分がどうしようもなく馬鹿らしく思えた。 そうして、少しずつ俺は変わったと思う。今もまだ、暗闇の記憶は付きまとうけれど……。 「団長、ただいま帰りました」 前置きもなく、ドアが開かれた。現れたのはシリウスと同じ顔をした青年。リゲル・ダリア、シリウスの双子の弟。シリウスとは違い、雪解けの水のような透明な魔力の印象。肩まで伸びた銀髪を首の後ろで一つにまとめているのが、魔力を持たない人間がこの双子の見分ける方法だ。 しかし、表情を一見すれば明らかな違いは明確だった。 同じ類稀なる美貌を有しているが、片方は冷酷で、片方は穏健な眼差し。唇に浮かべる感情も、対照的だった。 「あ、シリウスも帰ってきてたんだ」 リゲルは――魔力を持っている魔法師にとって、壁一枚隔てても同じ魔力を持つ者相手なら、見誤ったりしない。魔力はそれほどに個々人の特徴を映していたから――まるで、今、気がついたといった感じでそんなことを口にした。 常にそれぞれの魔力と接していると、特別意識することもなくなってしまうこともままある。 先程、シリウスが俺に確認を取ったのは、もう彼にとって俺は空気のような存在となり、魔力をわざわざ知覚する必然性を感じていなかったからだ。 ようするに、俺の接近を気にかけていなかったからだ。 だから、リゲルの言葉も、特別、変なことではない。 けれど、リゲルの唇に浮かべた愛想のいい笑みに、微かながら緊張に似た強張りがあったなら、それは違った意味を持ってくる。 初めて気がついたようなふりをして、何事もなかったように声を掛ける。 意図的に構えて話しかけたとして、リゲルの声はシリウスには届かない。 何故なら、何を言おうとするのか、もう既にわかりきっているから。 でも、どんな風に装っても、リゲルの望みはシリウスが望むものとは違うから、この双子の間にある狭間は埋められない。 続けてリゲルが何かしら口にしようとしたところで、ディードは書類にサインをし終えた。シリウスはサッとディードの手から書類を奪う。 「それでは失礼します」 微かに頭を下げると、シリウスは回れ右で、リゲルが開け放ったままのドアから出て行った。弟を一瞥することもなく。 「……オイ」 呆気にとられたディードが声を発したときには、シリウスはもうドアを閉じていた。俺たちの前には片腕を上げた状態で笑みを凍りつかせたリゲルが取り残される。 「……む、無視された」 ガックリとうなだれたリゲルにディードが嘆息を吐きつつ、言った。 「……それって、いつものことだろ?」 「そうですけど。どうして、俺にはあんなに素っ気ないかな。仮にも弟ですよ?」 「同じ面下げて、他人なんて言うほうが、無理があると思うが?」 つまらないあげ足をとって、ディードは意地悪く笑う。こういうところは子供っぽい。普段、童顔をからかわれているディードは機会を見つけては、こういう小さいところで仕返しをしてくる。 俺も男とも女ともつかない中性的な顔立ちを何度、揶揄されたことか。こちらとしても、彼が最大限に気にしている童顔を口にしているので、人のことは言えない。 「でも、この世にたった一人しかいない弟ですよ。よう、お疲れ、とか言ってくれても良いじゃないですか」 「シリウスがそれを口にしたら、逆に気味が悪いと思うぞ?」 ディードが片眉をひそめて、嫌そうに言った。 無表情というより、自分に近づく者、全てを拒絶するようなシリウスが、ディードの言う通りにそんなことを口にしようものなら、大抵の人間は天変地異が起こりやしないかと恐れ、慄くだろう。 誰に対しても触れることを許さない、冷ややかさで、シリウスは心を凍らせた。 その昔、俺が心を殺したように。 その凍った心をとかすのは並大抵のことではない。 「……まあ、そうですけどね」 微苦笑をして、リゲルは肩を竦めた。 同じ顔をしたリゲルが気さくな口を利いても、全く、違和感がない。 双子なのに、全然違う。 ふと、リゲルが俺を見た。青灰色の瞳は冷たさではなく穏やかさが覗く。 「でも、ロベルトにはシリウスは普通だよな?」 「そうですか?」 俺は笑みを返して、首を傾げる。ディードが「そういえば、そうだな」と唸るように呟いた。 「……だとしたら、それはシリウスさんにとって、俺は無害だからですよ」 「それって、俺が有害ってことか?」 「有害……とは違います。でも、少なからず、シリウスさんに影響を与えるでしょう、リゲルさんは」 「影響って?」 「シリウスさんは、今の状態を変えたくないんですよ」 「今の状態って……リゲルと和解したくないってことか?」 ディードの言葉に、リゲルは「そんなー」と情けない声を上げた。せっかくの美貌も台無しの表情を作る。それはシリウスには真似出来ないことだ。 「和解したくないとか、そんなこと以前の問題だと思います。シリウスさんは……誰にも自分に関わって欲しくないんですよ」 昔の俺がそうだった。 誰にも俺のことを理解して欲しいとは思わなかった。俺自身が誰のことも理解するつもりがなかったから。 世界は俺の思いに関係なくそこにあり続ける。だったら、俺に関係なくそのまま、あり続けていればよかった。 誰も俺なんかのことを顧みることもなく。 俺はただ死ぬことが出来なかった故に生きているような人間だったから。 シリウスはそんな俺とは、ちょっと違うだろう。彼は生きることに拒否しているわけではない。ただ、自分の人生に人が関わるのを拒否しているのだ。 「心の闇に――傷に、誰にも触れて欲しくなんですよ、シリウスさんは」 シリウスが人を拒絶するのは他でもない、精神を病んだ母親に監禁されて育ったからだ。 俺は愛人の息子であったがために正妻に虐待されて、育った。 シリウスとは境遇が似ているといえば、似ているだろう。 もっとも彼の場合は過度の愛情が、監禁という行為に出た。愛されすぎた故の悲劇とでも言おうか。母親はシリウスを守ろうとして、彼を地下室へと閉じ込めたのだ。 だが、そこにどんな理由があったにしろ、シリウスがそのことによって人間というものに不信感を抱いたのは変わらない。その不信感が心を凍らせた。 誰も近づくなと、冷たい目線で他人を拒絶して、幼い頃に生き別れた弟のリゲルにさえ、心を開くことはなかった。 「でも、リゲルさんは……シリウスさんに兄弟としての関係を求めるでしょう」 俺が視線を投げると、リゲルは言葉に詰まるように顔を顰めた。 「シリウスさんはそんな風に、他人と関係したくないんですよ」 「じゃあ、お前とは? 何で、お前なら無害なんだよ?」 納得がいかないと、ディードが問う。 「俺は……シリウスさんの心の傷に唯一、触れられない人間だからですよ」 こう言ったところで、ディードには伝わるだろうか? リゲルには? 二人を見ると、わからないと言いたげな表情がそこにある。 ……わからないから、傷に触れようとする。傷を癒そうとする。心を溶かそうとする。 癒される傷というものもあるだろう。 けれど、癒されない傷というものもあるし、癒すという過程で傷と向き合うことを拒絶したい心理というのもあるのだ。 己の中にある心の暗闇を、見たくはないと願う人間もいる。 シリウスは自分が負った傷を見たくはないのだ。 愛されたということを知りたくない。愛されれば、また、同じようなことが繰り返されるかもしれない可能性を、彼は拒絶している。 だから、誰にも心を開かない。愛されたくないから……。 人と関わりを持たなければ、もう傷つくことがないと、そう信じていたいのだ。 「俺にも……傷があります」 そっと自分の胸に手を当てて呟いた俺に、リゲルは痛ましそうに目を伏せた。 この手の下、宮廷魔法師の制服の下に隠されているのは虐待の傷跡。 もう、この王宮内で俺の過去を知らない者はいない。 「俺はこの傷に触れたくない。昔の自分に帰りたくはないです」 心を殺していた自分に戻りたくはないと、思う自分がいた。全てはディードに出会ってから。彼に出会って、感情に縛られず自由に生きることに憧れた。自分もそんな風になれたらと、思ったとき、俺の心は息を吹き返した。 「だから、同じようにシリウスさんの傷には触れられないんです。俺自身が、シリウスさんに対して、触れられることを拒むから」 互いに思うことが理解しあえるから、一定の距離を維持できる。 リゲルのように踏み込んでくる心配がない。 「……わけ、わかんねぇよ」 ディードは唇を尖らせた。そういう子供っぽい所作が、童顔の彼には良く似合う。 怒ったり、笑ったりとコロコロと表情が変わるディードに、俺は目を細めた。その自由さがたまらなく眩しい。 謀反人の息子という汚名を着せられながら、決して屈することなく前を見て歩いていくディードには己の闇を払拭する光がある。 暗闇の記憶に囚われている俺やシリウスとは別次元の人種だ。 だから、わからない。傷に触れることで、触れられることで……いとも簡単に揺らいでしまう弱さを。 シリウスが自我を保つには、他人を拒絶するしかない。それが彼の最後の矜持。暗闇に囚われないための手段。 囚われてしまったら……心を凍らせるだけではすまない。他人を拒絶するのは、まだ他人を他人と認識できる範囲にいる。 他人を拒絶するのではなく、他人の存在から自分自身の存在まで放棄してしまった俺より、まだシリウスはギリギリのラインで自分を保っていた。 でも、闇はそこにあるから……。 「今のバランスを壊して欲しくない、それだけなんですよ」 「……でも、それだったらっ!」 リゲルが顔を歪めて声を荒げた。 「俺はシリウスに拒絶されるしかないのか? 兄弟なんだぞ?」 「……シリウスさんを傷つけたのは、お母様ですよ」 俺の返した言葉にリゲルは言葉に詰まる。 わざと傷つけたわけじゃない。精神を病んでいたのだ。 だけど、傷つけられた事実は変えられない。その事実を前にすれば、どんな言い訳も通用しない。 「シリウスさんは例え、リゲルさんでも傷に触れて欲しくない。だから、そっとしておいて欲しいんです」 「それしか、リゲルにはできることがないってか?」 ディードが問う。俺は頷くしかなかった。 「そうですね。今は、それしかないでしょう」 「お前も触れて欲しくないって言ったよな。じゃあ、お前も他人に関わりたくないのか?」 「俺は……昔とは違って、変わったでしょう?」 「そうだな。昔は死んだ魚みたいな目をしてた」 「……それはもう言わないでください」 苦笑して、軽くディードを睨む。 死ねなかったから生きていただけの、昔の俺の目は、死んだ魚のように虚ろな瞳をしていたと誰からも言われた。 死んだ魚の目。虚空を見つめる空虚な視線。目の前の現実を見つめるわけでもなく、ただただ目に映るものを鏡のように映すだけ。 「今は……あのことを思い出すのは嫌ですけど。でも、俺は王宮に上がって、色々な方と出会って、決して自分だけが不幸じゃなかったって知って……」 ディードやシリウスだけじゃない。人はそれぞれに傷を抱え、暗闇を持っていることを知った。 リゲルだって、実の兄であるシリウスに受け入れられてもらえないことに、傷ついている。 「誰かと比べて、自分の方がまだマシだとか、そういうんじゃないんです。ただ今の俺は……」 視線を上げると、エメラルドグリーンの瞳を見つめた。 「こうやって、笑い合えることを嬉しいと思うから、他人と関係することが嫌じゃないんです」 そっと笑いかけると、ディードは唇の端を吊り上げるようにして笑った。 「いい傾向じゃねぇか」 「はい。……自分でも驚きますけどね」 あの暗闇のなかで息をひそめていた頃、もう二度と笑うことなんてないと思っていた。 「どうしたら、そんなに変われたんだ、ロベルトは。シリウスはもう駄目なのか? 変われないのか?」 「俺はシリウスさんじゃないから、どうしたら、シリウスさんの傷を癒せるのかわかりません。今はただ、そっとしておいて欲しいというくらいしか。でも、そう望むってことは、シリウスさんにとって、それは傷を癒すための期間なのかもしれません」 他人を他人と認識しているのなら、まだ、人間に対して絶望していないのだ。 「拒絶しているということは、それだけの距離が必要なんですよ。シリウスさんにとって、他人は。俺は端から踏み込めないけれど、リゲルさんは躊躇なく踏み込んでしまう。でも、今はリゲルさんでも自分の領域に踏み込んで欲しくないと、シリウスさんが望んでいるのなら、シリウスさんの意思を尊重してください」 「それが、シリウスに対して、俺にできることなのか?」 「……多分」 本当のところは、俺にはわからない。 他人が土足で自分の領域に踏み込んでくるなんてことすら、俺には関係なかった。自分の領域すら、放棄してしまった俺だったから、守るべき矜持も何もなかった。 「…………」 リゲルは黙り込むと、俯いた。暫くして、くるりと踵を返すと部屋を出て行った。前置きもなしに行動するところは、シリウスと似ている。 「……あいつ、任務報告に来たんじゃなかったのよ?」 パタリと音を立てて閉じるドアに、ディードは呆然と呟く。 「……リゲルさん、気を悪くされたんでしょうか」 少し不安になって問いかけると、ディードは軽く肩を竦めた。 「リゲルに限って、それはないだろ。お前の言い分が本当のところ、どうなのか確かめに行ったんだろうさ」 「確かめるって、どこに」 「だから……シリウスのところだろ?」 「それ、本末転倒」 「……だよな。まあ、少し自分なりに考えてみるだろうが、二、三日が限界だろうぜ。あいつもな、シリウスのことさえなけりゃあ、優秀なのに」 どうしようもない、と言いたげにディードは首を振ると、やがて思い出したように俺を見た。 「そうだ、お前を呼び出したのは他でもない――」 ディードの執務室を出て、俺は宮廷魔法師団の寮に戻る。そうして、書庫へと向かうと時間潰しに本を読んでいたのか、シリウスがいた。 他人との関係を拒むシリウスはこういうところで時間を潰すことしか知らないようだ。 「あ、シリウスさん」 「……ロベルトか。団長のところから戻ってきたのか」 声を掛けると、シリウスは魔法書から顔を上げ、冷たい青灰色の瞳で俺を一瞥した。 「ええ。聞いてくださいよ。俺が団長に呼び出された理由、何だったと思います?」 「何だ?」 「報告書の字が汚いですって」 俺はディードから突っ返された報告書の書類をシリウスに見せた。 自分で言うのも何なんだが、俺の字は汚かった。これはまあ、しょうがないのだ。一応、貴族家庭の跡取り息子として、教育は受けたものの、俺の身体はいつもどこかに殴られた青痣があった。 家庭教師たちも正妻の虐待を黙認していた状況で、身体の痛みを訴えられはしない。故にその痛みを庇う姿勢で学習し、文字を書くことを覚えてしまった。 それで今も不自然な文字の書き方をしてしまう。 ディードのいうところ、ミミズがのたくりまわったようなと、評価されるような。 いつもは時間を掛けて書くことで、何とか見れた報告書を提出していたが、今回は期限が迫っていたため急ぎ仕上げた結果、付き返される羽目になった。 「今から書き直しです。まあ、時間を掛ければ読める文字にはなると思うんですけど」 俺は笑った。シリウスからは冷たい一瞥しか返ってこない。 だが、彼は俺がここにいることを拒絶したりはしない。 そっと魔法書に視線を戻すシリウスに、俺は向かいの席について書類の書き直しに入る。 静かな空間にペンの走る音が微かに響く。 息をひそめるようにして俺たちは、ただただ、一定の距離を踏み込むことなく保ちながら存在する。 傷を舐めあうこともできない俺たちは、暗闇の記憶に震えているしかない。 ディードのように自らの闇を払拭する強さもなければ、リゲルのように嫌われるのを覚悟して変化をもたらそうと行動する勇気もない。 でも、いつか……。 この記憶を笑い飛ばせるようになれればと、願う想いは……。 「明日……晴れるといいですね」 「……そうだな」 ポツリと呟いた言葉にのせて……。 …………どうか、未来に。 夜が来ても、やがて朝が来るように、明日へ届きますように……。 「暗闇の記憶 完」 |